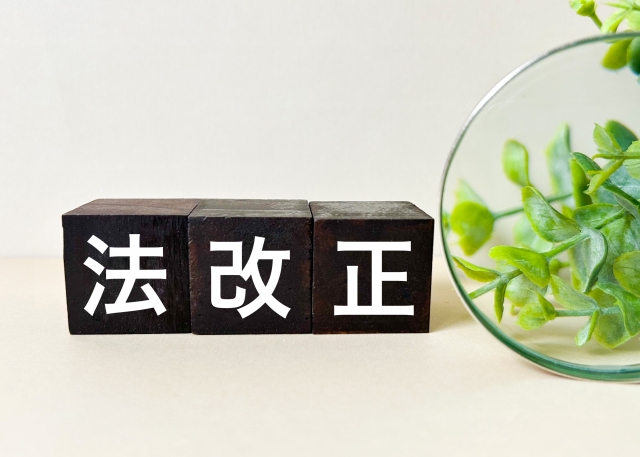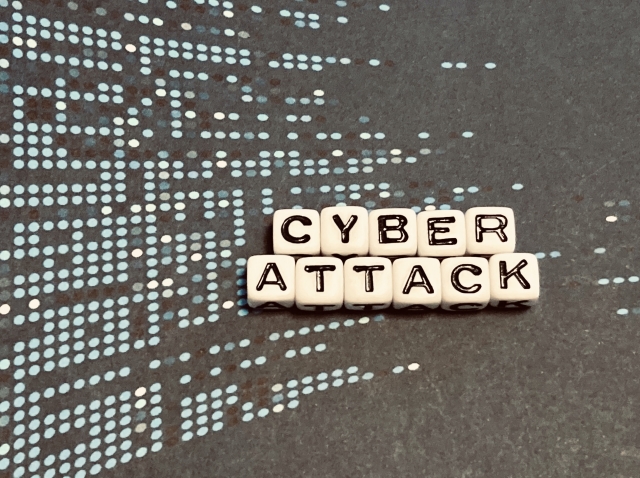2025年8月29日、金融庁が令和8年(2026年)度税制改正要望を公表しました。この中でも特に一般投資家の皆様に大きく影響する「NISA制度のさらなる拡充」「暗号資産の分離課税導入」「金融商品の損益通算範囲拡大」の3つのポイントについて、分かりやすく解説いたします。
これらの改正が実現すれば、投資環境が大きく変わる可能性があります。どのような変化が期待され、私たち投資家はどう準備すべきかを一緒に見ていきましょう。
- 金融庁が令和8年度税制改正要望を公表した
- 個人投資家に影響のある要望は、NISA制度の更なる拡充、暗号資産の分離課税導入、金融商品の損益通算範囲の拡大の3点である
- NISA制度では、つみたて投資枠における対象年齢の見直し、対象商品の拡充、非課税保有限度額の当年中の復活が要求されている
- 暗号資産については、現行の総合課税の扱いから分離課税の扱いへの変更が要求されている
- 損益通算範囲の拡大では、FXや先物取引などのデリバティブ取引や、預貯金の利子等を対象に含めることが要求されている
税制改正要望のポイント
「税制改正要望」とは、税制に関して「こう変えてほしい」という要望を、国が受け付ける制度です。 税負担の軽減や制度の合理化などを目的に、毎年夏頃に提出され、政策検討の出発点となります。 要望はそのまま法律になるわけではありませんが、税制改正の議論の入口として重視されています。
税制改正の一般的なスケジュールは以下のとおりです。
- 12月:税制改正大綱で方針決定
- 3月:税制改正法案成立
- 翌年1月:新制度開始(早ければ2026年1月~)
金融庁は「資産運用立国」の実現に向けて、個人投資家の裾野拡大を本格的に進めています。今回の税制改正要望のうち、個人投資家に影響があるポイントは以下のとおりです。
- NISA制度の更なる使い勝手向上による投資促進
- 暗号資産投資に係る課税の見直し
- 金融商品に係る損益通算範囲の拡大
それぞれのポイントについて、解説していきます。
NISA制度に関する要望
まず、現行のNISA制度をおさらいしておきましょう。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間の投資上限額 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無制限 | |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円 | |
| 1,200万円(内数) | ||
| 非課税保有限度額の復活 | 売却した商品の取得金額の分だけ翌年に復活 | |
| 投資対象商品 | 積立・分散投資に適した 一定の投資信託 | 一定の条件を満たした 上場株式・投資信託等 |
| 投資方法 | 定期かつ継続的な方法 | 制限なし |
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
金融庁NISA特設サイト「NISAを知る」より引用(一部改変)
今回改正が要望されているのは、以下の3点です。
- 子ども支援の一環としての、つみたて投資枠における対象年齢の見直し
- 様々な投資運用ニーズに応えるための、対象商品の拡充等
- 投資商品の入替をしやすくするための、非課税保有限度額の当年中の復活
金融庁「令和8年度税制改正要望について」より引用
一点目は、子どもの資産形成に関するものです。18歳未満が加入可能だったジュニアNISAが2023年で廃止になっており、この代替となる制度として、つみたて投資枠の対象年齢を引き下げることが要求されているものです。
二点目は、様々なニーズに応えるために、対象商品を広げる要望です。どのような商品に拡大するかは資料には書かれていませんが、「毎月分配型」の投資信託なども検討に入ってくるものと思われます。
三点目は、保有限度額の枠を売却直後に復活させることができるようにすることで、より機動的な運用を可能にする要望です。
これらが実現すれば、NISAがさらに使いやすくなるでしょう。
暗号資産取引に係る課税の見直し
現行の税制では、暗号資産等の仮想通貨は原則として雑所得扱いとなるため、総合課税の対象です。 つまり、給与所得やその他の所得がある場合は、仮想通貨に関する雑所得を、その他の所得に加えた総所得に対して、所得税や住民税が課税されます。総合課税は、超過累進課税により、税率は5%から最大45%になっています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
国税庁「所得税の税率」より引用
一方で、上場株式等の譲渡所得、および配当所得については、税率20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別税0.315%)の申告分離課税となっています。
暗号資産への投資が増加する中、昨年の税制改正大綱において、見直しの検討が示唆されています。
第三 検討事項
3 暗号資産取引に係る課税については、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置付け、上場株式等をはじめとした課税の特例が設けられている他の金融商品と同等の投資家保護のための説明義務や適合性等の規制などの必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提に、その見直しを検討する。
自由民主党・公明党「令和7年度税制改正大綱」より引用
このような状況の中、今回の税制改正要望では、以下が要望として挙げられています。
暗号資産取引に係る必要な法整備と併せて、分離課税の導入を含めた暗号資産取引等に係る課税の見直しを行うこと。
金融庁「令和8年度税制改正要望について」より引用
法整備との兼ね合いで時間がかかる可能性がありますが、大きな流れとしては暗号資産を金融商品として位置付けていくことになると思います。
また、アメリカでビットコインETFが承認された流れを受け、日本でも暗号資産ETFの組成が可能になる可能性があります。これにより、より手軽で安全な暗号資産投資の選択肢が広がるかもしれません。
金融商品に係る損益通算範囲の拡大
上場株式等(上場株式、公募株式投信、特定公社債、公募公社債投信など)は、その範囲において損益通算をすることができます。しかし、FXや先物取引を含むデリバティブ取引は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。また、預貯金の利子については、源泉分離課税であり、これも損益通算は認められていません。
- 国税庁確定申告書等作成コーナー「上場株式等とは」
- 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
- 国税庁「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」
- 国税庁「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」
このような状況の中、昨年の税制改正大綱において、見直しが示唆されています。
第三 検討事項
2 デリバティブ取引に係る金融所得課税の更なる一体化については、意図的な租税回避行為を防止するための方策等に関するこれまでの検討の成果を踏まえ、総合的に検討する。
自由民主党・公明党「令和7年度税制改正大綱」より引用
こうした示唆を受け、今回の税制改正要望では、以下が要望として挙げられています。
投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備を図り、家計による成長資金の供給拡大等を促進する観点から、金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等にまで拡大すること。
金融庁「令和8年度税制改正要望について」より引用
この要望が実現されれば、先物取引の損出を上場株式の利益と相殺したり、上場株式の損出をFXの利益と相殺できるようになります。
租税回避防止策の実現など新たな規制とも絡むので、実現には少し時間がかかるのかもしれませんが、投資を促進する改正なので早期に実現して欲しいものです。
まとめ
金融庁が公表した令和8年度税制改正要望のうち、個人投資家への影響の大きい3項目について解説を行いました。制度改正には時間がかかりますし、必ずしも要望が実現されるわけでもないので、まずは現行制度でポートフォリオを最適化しつつ、これらの要望がどのような形で12月の税制改正大綱に盛り込まれるか注視していくことが良いと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー